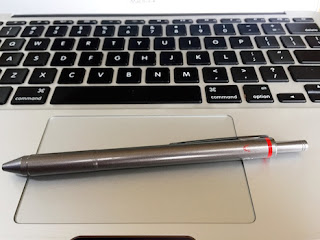芯ホルダーを使う /鉛筆とシャープペンシルの中間

芯ホルダーという筆記具をご存知でしょうか。図面を描く人にはメジャーで、建築系の人ならお馴染みだと思います。シャープペンシルのような鉛筆のような存在で、鉛筆と同じ2mmの芯を使うシャープペンシルだと思ってください。私は三菱鉛筆とステッドラーの芯ホルダーを使っていますが、過去にはカランダッシュやファーバーカステル、ロットリングなども使っていました。慣れるとシャープペンシルよりも使い勝手が良かったりするんです。 初めての芯ホルダー 私は大学の建築科を出ているので、学生時代に使ったのが最初です。三菱鉛筆の芯ホルダーで、周りには使っている人が結構いました。しかし当時は図面を描くのにシャープペンシルの方が都合がよく、しばらく使ってからほとんど触ることはありませんでした。再び芯ホルダーを使うのは、社会人になって建設会社に就職してからです。 現場監督だった私は、図面をシャープペンシルで描き、現場で芯ホルダーを使っていました。ステッドラーの芯ホルダーをもらったので、赤い芯を入れていました。現場ではコンクリートの壁やベニヤ板に絵を描いて職人に説明したり相談することがあり、その時に使っていました。鉛筆でも良かったのですが、鉛筆だとしょっちゅう削らなくてはいけません。コンクリートに書くと、あっという間に芯がなくなるのです。だから削る手間がない芯ホルダーは便利でした。 芯ホルダーの良さ 先にも書いたように、削る必要がないことです。そして鉛筆と同じように、紙で芯をこすって好みの太さに変えることができます。太い線も細い線も1本で描けます。シャープペンシルだと太さを変えて何本か持つしかありませんが、芯ホルダーは一本で大抵のことがこなせてしまいます。 私は図面を描くときはシャープペンシルを使うと描きましたが、0.4mmと0.9mmの2本を使い分けていました。極細の線を描きたいときは0.4mmを紙でこすって尖らせて0.3mmや0.2mmの太さにし、太く描きたいときは芯を斜めにして0.5mmくらいの太さで描いていました。通り芯と呼ばれる基準線は0.9mmの太いペンを使っていました。しかし芯ホルダーを上手く使うと、一本でこれらのことができてしまうのです。 ノック式とドロップ式 芯ホルダーは、お尻をノックして芯を出します。しかし芯の出方には2種類あり、好みが分か...