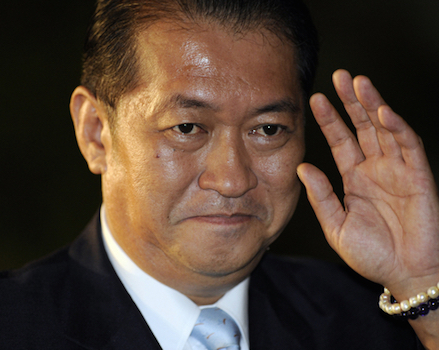第二次世界大戦を関ヶ原の合戦に例えると /日本が常任理事国になるには

2022年5月23日、日米首脳会談でアメリカのバイデン大統領が国連の安保理改革が実現した場合には、日本が常任理事国になることを支持したと報じられました。しかし日本が国連の常任理事国になることはあるのでしょうか?それを考えるには、第二次世界大戦を関ヶ原に、国連を江戸幕府に例えるとわかりやすいと思うので、今回はその話を書いてみます。 関ヶ原の合戦とは 豊臣秀吉は天下統一を実現しましたが、秀吉の死後は独裁体制から脱皮して徳川家康や前田利家らの五大老が治める政治体制に移行しました。しかし五大老の政治抗争が始まり、この体制は徐々に崩壊していきます。この政治抗争は紆余曲折を経て、徳川家康と豊臣家再興を目指す石田三成との争いが関ヶ原で決戦を迎えることになりました。 この戦いに徳川家康は勝利し、江戸幕府を開いて長期政権を築くことになります。家康は自分とともに戦ってくれた大名と、関ヶ原の合戦に敗れて徳川に就いた大名を明確に分けました。石田三成の配下だった大名は外様と呼ばれ、僻地へ左遷されて幕府の要職を任されることもありませんでした。有名な外様大名には島津家(薩摩藩)や毛利家(長州藩)、前田家(加賀藩)などがあります。 明治維新での逆転 外様大名は何かと差別されており、些細なミスが原因で屋敷を取り上げられたり身分を剥奪されたりと、何かと不利な立場に置かれていました。要職を与えず、僻地に飛ばし、参勤交代で財産を溜め込まないようにし、常に裏切らないように目をつけていたのです。徳川幕府にとって外様はいつまで経っても豊臣側であり、真の味方ではなかったのです。その一方で、関ヶ原で最初から味方だった大名は譜代大名と呼ばれ、いつも重用されるのは彼らでした。 この立場が逆転するのは明治維新です。薩摩藩や長州藩などの外様が中心になり、幕府を倒して明治政府を立ち上げました。将軍徳川慶喜は天皇に政権を返上したものの、依然として政府への影響力を維持しようとしたとされていますが、戊辰戦争などを経て徳川家は政権から完全に追い出されました。こうして260年以上も続いた江戸幕府は終わり、外様大名が政府の中心に就くことになりました。 日本は外様大名 第二次世界大戦を関ヶ原に置き換えると、アメリカやイギリスの連合国は徳川軍でドイツ・イタリア・日本らの枢軸国は石田三成軍です。そして連合国が勝利し、その後の国際秩序...