シリーズを通して007を考える /何度も変わった作風を追ってみよう
007シリーズは、1962年に公開された「007 ドクター・ノオ」から「007 スペクター」までシリーズ累計24作が作られています。しかし主演俳優の交代や監督の変化、時代背景によって大きく性質が変わっています。今回は007シリーズの時期ごとに異なる魅力や特徴について解説していきたいと思います。
小説版の007
大戦中に諜報員として働いたこともあるイアン・フレミングは、イギリスで多く手がけられていた地味で重厚な本格派スパイ小説とは異なる娯楽的要素の強いスパイ小説を書くことにします。当時のイギリスのスパイ小説は難解で暗い話が多く、読みやすいとは言えない重厚さが売りでした。そこでもっと読みやすい軽快なスパイ小説を書くことにしたのです。しかしアメリカで大流行していたハードボイルド小説の影響もあり、フレミングはシビアでハードなアクションを物語に盛り込むことにします。
テレンス・ヤングとガイ・ハミルトンの時代
映画化にあたって監督を任されたテレンス・ヤングは、ボンド役に無名のショーン・コネリーを抜擢します。スーツを着た経験がないコネリーの起用は大胆で、原作者のフレミングはもっと有名な俳優を希望しています。しかしカメラ映りの良さに加え、フレミングの原作に影響されすぎない独自のボンド像を作ることが目的でした。そしてヤングはボンドの方向性を試行錯誤していきます。シリアスなスパイ物語にするか、コメディ路線にするか、ヤングだけでなくプロデューサーの間でも007は揺れ動きます。
「ドクター・ノオ」は荒唐無稽なアクションでありながら、一定のシリアスさとパロディやジョークを盛り込んで予想外のヒットになりました。このヒットにより製作された次作の「ロシアより愛をこめて」では、ジョークもパロディも排してシリアスな演出で前作以上のヒットを記録しました。しかしプロデューサーのアルバート・ブロッコリは、更なる娯楽色を求めます。ブロッコリはジェームズ・ボンドがスパイのアイコンになることを確信し、それには誰もが楽しめる娯楽性の高い作品が必要だと考えたのです。そして呼ばれた監督がガイ・ハミルトンです。
 |
| ※「ドクター・ノオ」の一幕 |
ハミルトンが監督した第3作目の「ゴールドフィンガー」は、大ヒットして007の方向性を決定づけました。あらゆる荒唐無稽な設定にジョークが散りばめられ、任務遂行よりもしばしば情事を優先するボンドができあがります。そして本作ではボンドカーが登場し、大きな話題をさらいました。高級車アストンマーチンに秘密兵器を満載にした巨大な玩具ともいえるボンドカーは、当時としては画期的なアイデアでした。この情事が大好きなプレイボーイのボンドのキャラと、数々の秘密兵器は以降の人気を決定的にしました。
 |
| ※「ゴールドフィンガー」のゴールドフィンガーとオッドジョブ |
1億ドルを超える大ヒットを飛ばした「ゴールドフィンガー」の次回作には、再びテレンス・ヤングが招聘されます。共同プロデューサーのハリー・サルツマンはブロッコリの娯楽大作化には懐疑的でした。下品なスパイではなくシリアスで緊張感のある物語を望んだサルツマンは、「サンダーボール作戦」では落ち着いたトーンを求めました。美女と会ったら即セッ○スに持ち込むボンドはそのまま活かされるものの、全体的にシリアスな演出が施されています。そして「ゴールドフィンガー」を上回る興行収入を得ることになります。
これにより、007はシリアス路線に行くかと思われました。しかしここからさらに激しく揺れ動くことになります。超娯楽路線に走りたいアルバート・ブロッコリと、シリアス路線を求めるハリー・サルツマンは、共同プロデューサーでありながらしばしば意見を対立させることになります。これが後に悲劇を生むことになりました。
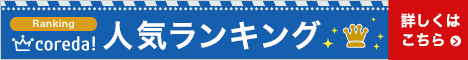

ブロスナン自身も、プライベートで問題を抱えていました。妻の死後、息子がアルコール中毒になるなど、子供達の非行に手を焼いていました。こうした経緯から、イオン・プロダクションはブロスナンの降板を決定します。苦渋の選択ではありましたが、マンネリ化が止められない007に、新たな息吹が必要でした。ブロスナンとしてはまだまだ続けるつもりだったようで、突然の知らせにショックを受けています。
ルイス・ギルバートの衝撃
新たに監督に招聘されたのは、コメディ映画を手がけていたルイス・ギルバートでした。彼は「007は二度死ぬ」で、そのコメディの手腕を遺憾なく発揮します。物語は荒唐無稽な設定に、全編がジョークとおふざけで満たされました。特に日本人から見ると、ボンドが日本人に変装する場面などは、悪い冗談にしか見えません。日本には存在しない諜報機関が登場し、特殊部隊が忍者という悪ノリばかりが目につきました。
さらにギルバートは玩具ともいえる秘密兵器をふんだんに用意し、それらを派手に使うことにも手を抜きませんでした。本作によって007は、アクションを含んだコメディ映画になりました。製作費の大半をクライマックスのロケット基地のセットに使う大胆な予算配分で、全体的にチープさが漂うことになります。しかしギルバートの狙ったコメディ路線にとっては大した問題ではありませんでした。そして「007は二度死ぬ」も大ヒットしました。
 |
| ※「007は二度死ぬ」で日本人に変装したボンド |
アルバート・ブロッコリのエンターテーメント性が発揮された作品ですが、悪ふざけとも言える演出に、もう1人のプロデュサーのサルツマンは大いに不満でした。さらにショーン・コネリーの不満を募らせていました。同じシリーズばかりに出続けることで役者としてのイメージが固定されることに加え、馬鹿馬鹿しいコメディにうんざりしてもいました。そこで次回作のオファーを断わることにしました。ここで007シリーズは岐路に立たされます。
新しいジェームズ・ボンドはジョージ・レーゼンビーに決まり、「女王陛下の007」はサルツマンの主導で原作回帰を狙って製作されました。監督は前作で助監督を務めたピーター・ハントを抜擢し、ハードボイルド路線で製作されます。しかしオーストラリア出身のレーゼンビーがイギリス訛りに苦戦し、さらに契約上の問題で揉めます。スタントマンではなく自身がアクションの多くをこなすことになったレーゼンビーは、契約書に記載がないと不満をぶちまけました。
 |
| ※「女王陛下の007」のジョージ・レーゼンビー |
モデル出身で演技経験がなく、イギリス式アクセントに苦戦するという苦難続きの中で、スタントマンがこなす仕事までやらされるのは負担が大きすぎたのです。レーゼンビーにとって初めてのことが多すぎたのですが、これは観客にとってもはじめてずくしの映画でした。慣れ親しんだコネリーから主役が変わり、ボンドが「君だけを愛する」と言って結婚するのも衝撃でした。結果的に本作はレーゼンビーにとっても観客にとっても不幸な作品となり、興行成績はノルマともいえる1億ドルを大きく割り込んでしまいます。サルツマンのシリアス路線は、この失敗で終焉を迎えるのです。次回作以降、007シリーズはお色気アクションコメディとしての娯楽性を発揮するようになります。
ガイ・ハミルトンの復権
「ダイヤモンドは永遠に」では、「ゴールドフィンガー」のガイ・ハミルトンを招聘し、ショーン・コネリーを復活させました。コネリーには120万ドルという破格のギャラが払われるものの、やる気を見せないコネリーは明らかに太っていました。ハミルトンはコメディの手腕を発揮し、再び007を荒唐無稽なアクションコメディにしていきます。
史上最低のカーチェイスを言われるコミカルでダルい月面車のカーチェイスや、ボンドガールのドジっ子ぶりに、パンツに入れたカセットテープで世界が救われるオチは、ハミルトンならではの演出です。「ダイヤモンドは永遠に」が大ヒットすると、エンターテーメント指向のブロッコリがプロデュースの主導権を握り、007のコメディ路線が決定的になります。
 |
| ※「ダイヤモンドは永遠に」の月面車のカーチェイス |
そしてこの映画では新たな流れが生まれます。カーチェイスにイギリス車ではなくフォード社のマスタングを使用したのです。これはマックイーンの大ヒット映画「ブリット」の影響が明らかでした。これまでアストンマーチンなど独自路線で多くの影響を与えてきた007が、影響を受ける側に回った象徴的な作品です。製作費の高騰から確実にヒットさせなくてはならなくなった007シリーズは、流行を作る側から流行に乗るようになったのです。そしてショーン・コネリーは、これを最後に2度とジェームズ・ボンド役はやらないと以降のオファーを断り続けることになりました。
コメディ路線を明確にしたブロッコリとハミルトンは、当時のヒット映画の要素を大胆に取り入れ、007をパロディとして扱っていきます。新たにロジャー・ムーアをボンドに迎えた「死ぬのは奴らだ」「黄金中を持つ男」では、節操がないくらいに当時のヒット映画や話題性の高いものが盛り込んでいきました。
 |
| ※「黄金中を持つ男」の唯一の見せ場 |
映画「ダーティ・ハリー」で話題になった拳銃M29を使用し、ビートルズを解散して新たな活動を開始したポール・マッカートニーに主題歌を依頼します。「ビートルズは耳栓をして聴くこと」と言っていたボンドから、大きな変容です。「燃えよドラゴン」のヒットでカンフーがブームになると、これもすぐに取り入れて空手着を着たムーアが素手格闘を演じます。オカルト、神秘主義も拝借し、「ポセイドン・アドベンチャー」がヒットすると、傾いた船が舞台になります。ようするに、流行っているものならなんでも取り入れるのが007シリーズになったのです。
 |
| ※スローモーなカンフーアクションが笑えます。 |
観客の目を引くアクションと笑いが重要となり、社会背景やスパイの必然性は排除されていき、007はハリウッドに対抗できる娯楽映画としての足固めが施されていきます。もはやジェームズ・ボンドはスパイの非情な世界に生きるタフな男ではなく、愉快で女好きのおじさんになっていきました。パロディが満載の世界で軽快なジョークで女性をベッドに誘い、敵の襲撃を退けると別の女性とベッドを共にするのがボンドになりました。しかし「黄金銃を持つ男」が興行収入1億ドルを下回ったので、新たなテコ入れが必要になります。さらに共同プロデューサーのサルツマンが、原作とかけ離れたエンタメ路線に嫌気がさし、007の製作から降板すると電撃発表しました。
サルツマンはイオン・プロダクションの株をブロッコリではなく、ユナイテッド・アーティスツ(UA)に売却しました。ブロッコリへの批判の表れでしょう。経営権を手にしたUAは、ロジャー・ムーアの解任を迫ったりするなど、後の007の権利問題の火種を蒔くことになりました。その顛末は、以下の記事に詳しく書いています。
ルイス・ギルバートの再登板
「私を愛したスパイ」で招聘されたのは、「007は二度死ぬ」で荒唐無稽なコメディ路線を発揮したルイス・ギルバートでした。ギルバートはハミルトンのコメディ路線を継承し、大掛かりな舞台にボンドの活躍の場を移します。007シリーズの新たなテコ入れは、このスケールアップでした。観客の度肝を抜く壮大な物語に、笑いとエロスを散りばめたのです。
ギルバートはハミルトンのようにドジっ子ボンドガールを使いませんでしたが、コメディ・リリーフとして登場したペッパー保安官に代わってジョーズを悪役兼コメディ・リリーフとして採用します。そして海底基地という巨大で荒唐無稽な設定に加え、お洒落でユーモアのあるボンドを磨きつつ、ハミルトン同様に全編に笑いを散りばめます。異なるのはムーアの恐ろしくスローモーな肉体を使ったアクションを削り、秘密兵器としてのボンドカーを復活させたことでした。ムーアは高齢のため、素早く動くアクションに限界があったのです。
 |
| ※雨漏れが酷いロータス・エスプリが、海に潜るというのは皮肉のようにも見えます。 |
ボンドカーは「サンダーボール作戦」のアストンマーチンDB5が装備品として渡されて以降、秘密兵器としての登場はありませんでした。成り行きで乗った車や、他の諜報部員の車を使ってアクションをしていたに過ぎません。しかし「私を愛したスパイ」の水陸両用になるロータス・エスプリは、潜水艦になる無茶苦茶な設定で正真正銘の秘密兵器でした。
「スターウォーズ」「未知との遭遇」で空前のSFブームが起こると、次回作「ムーンレイカー」では舞台を宇宙に移します。ここではリアリティは欠片もないほど排し、とにかく笑えて楽しめる映画を目指したギルバートの方向性はピタリと当たります。「私を愛したスパイ」の大ヒットに続き、「ムーンレイカー」はシリーズ最高の興行成績を記録します。007は冒険活劇として、お色気アクションコメディの金字塔となりました。しかし人気の頂点に達した007シリーズを今後どのように続けていくのかが、新たな課題となりました。
 |
| ※人気の悪役ジョーズも「ムーンレイカー」で最期を迎えます。 |
ジョン・グレンの軌道修正
新たに監督に起用されたジョン・グレンは、いき過ぎたコメディから本格派のアクションへの転換を試みました。さらに宇宙まで行った前作は、さすがにやり過ぎとの批判があったので、地に足がついたボンドを構築する必要がありました。
「ユア・アイズ・オンリー」では、地に足が着いた本格的なアクションとして、スキーや空中スタントが使われます。これまで恐ろしくスローモーだったムーアのアクションは、スタントマンとのモンタージュ手法でスピーディに映し出され、「ムーンレイカー」とは別人のような動きが見られます。さらに美女なら誰であってもすぐにセッ○スに持ち込むボンドが、美女に復讐をとがめる人間的な場面も加えられました。「ユア・アイズ・オンリー」ではコメディも抑えられて、きわめて真面目なボンドが登場します。
しかしこれには不満があったのか、次作「オクトパシー」では大量の美女とコメディが復活しています。美女に会ったら即セッ○スに持ち込む展開も復活し、セクシーな美女軍団の登場に、ワニの被り物で潜水するボンドなど滑稽な設定も戻ってきます。しかし本格派アクションへの希求は変わらず、超小型ジェット機でのアクションは壮絶なものになりました。
 |
| ※「オクトパシー」でピエロに扮したボンド |
次作「美しき獲物たち」では、さすがにロジャー・ムーアの高齢ぶりが目立ち、ボンド役を降板します。実は生真面目なムーアにとってベッドシーンは苦行だったようで、撮影は毎回のように激しいストレスに苛まれていました。高齢になったことで、長年続けたジェームズ・ボンドを降板する決心をしたのです。
次にボンドに選ばれたティモシー・ダルトンは、グレンが求めた役者なのかもしれません。主役交代にともなって、コメディやお色気を排した原作回帰と本格派アクションが可能になりました。ダルトンは徹底した役作りに励み、銃の取り扱いの訓練も受けています。「リビング・デイ・ライツ」と「消されたライセンス」では、原作のようにボロボロになるまで戦い抜くボンドを演じています。
 |
| ※プロのような銃の扱い方を見せたティモシー・ダルトン |
特に「消されたライセンス」では、これまでにない血なまぐさいシークエンスを挿入し、リアリズムの追求がみられます。しかし観客の反応はイマイチでした。お洒落でユーモアがあり、美女に囲まれたボンドのイメージが強すぎたのでしょう。さらにイオン・プロダクションの大株主のMGM/UAが経営難ために売り出され、007の権利が宙に浮いてしまい次回作の製作の目処が立たなくなりました。
 |
| ※ボコボコにされるボンドを演じるティモシー・ダルトン |
この時点で、ダルトンは契約が1本残っていました。しかし5年後に製作が可能になるとプロデューサーのブロッコリは、再開した007に1本だけダルトンが出演して降板するのは興行的にまずいと判断し、さらに数本の出演をオファーします。しかし5年も待たされたダルトンは、さらに何年も007に拘束されることを嫌い、降板を決意します。イオン・プロダクションは、また新たなボンド役を探さなくてはならなくなりました。
ピアーズ・ブロスナンのボンド時代
ダルトンとグレンの原点回帰という野心的な試みは、セールスの面で成功しませんでした。そこでブロスナンが目指したのは、「ユーモア感覚と軽いイメージ」というムーア時代のボンドに加え、コネリー時代の洗練さをミックスしたものでした。さらにプロデューサーのブロッコリは、これまでと違って毎回監督を変えることで、マンネリを回避しようとします。そしてブロスナンの起用は当たり、「ゴールデンアイ」はダルトンの「消されたライセンス」を大きく上回る興行成績を収めました。
 |
| ※「ゴールデンアイ」の一幕 |
ブロスナンは、ムーアの軽さとコネリーのタフさを兼ね備えたボンドだと絶賛されますが、不運だったのは冷戦が終結し、国際的なイギリスの敵が不明確になってしまったことです。さらにこの頃になると、CGなどの多様が当然になり、製作費の高騰が始まりました。そのため、興行収入としてはダルトンの時代よりヒットしているものの、ダルトンは製作費の4倍から6倍の興行収入を得いていたのに対し、ブロスナンは3倍程度の興行収入しか得られていませんでした。
 |
| ※「トゥモロー・ネバー・ダイ」の一幕 |
ブロスナン自身も、プライベートで問題を抱えていました。妻の死後、息子がアルコール中毒になるなど、子供達の非行に手を焼いていました。こうした経緯から、イオン・プロダクションはブロスナンの降板を決定します。苦渋の選択ではありましたが、マンネリ化が止められない007に、新たな息吹が必要でした。ブロスナンとしてはまだまだ続けるつもりだったようで、突然の知らせにショックを受けています。
ダニエル・クレイグでの原作回帰
次のボンドが決まる前から、次回作は決まっていました。これまでは権利上の問題で、イオン・プロダクションが製作できなかった小説版第1作の「カジノ・ロワイヤル」です。そのため、次のボンド役は原作のイメージから検討が始まります。
さらにこれまでのボンドのイメージを一新し、ユーモアのある軽い印象を排して、原作通りの寡黙でタフなボンドをイメージします。労働者階級出身と一目でわかるクレイグが登用されたのは、この寡黙でタフなイメージによる部分が大きかったようです。
クレイグがボンドに決定すると、世界中でバッシングが起こりました。「髪が黒くない」「耳が大きすぎる」「背が低すぎる」などの外見による批判がほとんどで、鑑賞ボイコットの運動まで始まります。しかし「カジノ・ロワイヤル」が公開されると、その評価は一変し、大ヒットとなりました。
 |
| ※ティモシー・ダルトン以上のハードなボンドになりました。 |
クレイグのボンドは、これまでのボンドのイメージを捨て去りるため、原作回帰が行われました。ボンドカーにはアストンマーチンが用意され、拳銃はワルサーPPK/Sが戻ってきました。しかし原作回帰だけでなく、様々な変化が起こります。これは製作資金を集めるためのタイアップによるものです。
時計はオメガになり、マティーニではなくハイネケンをボンドは飲みます。スーツはトム・フォードになりました。オランダのビールを飲み、アメリカ人がデザインしたスーツを着るボンドに、違和感を覚える声もありましたが、伝統を気にせず新たな時代のボンドが作られたわけです。
 |
| ※ハイネケンを飲むボンド |
クレイグの契約は「スペクター」の後に、もう一本残っているようですが、クレイグの判断で降板が可能な内容のようです。次回作に否定的な発言を繰り返し、クレイグが降板するという噂が囁かれています。また新たなジェームズ・ボンドが、すぐそこまで来ているのかもしれません。それはそれで、楽しみでもありますね。



にほんブログ村
にほんブログ村







すばらしい考察! 007を語ってお金をいただくこともある私ですが、貴兄の卓論に比して、自ら説くところの貧弱を思います。
返信削除二点、お聴きしたいことがあります。
テレンス・ヤング監督は、『ロシアより愛をこめて』の「列車のなかのバトル」の演出からわかるように、「タイマン勝負」は的確に表現できる。しかし、『サンダーボール作戦』のクライマックス、ナトー軍とスペクターとの「原爆をめぐる戦い」は、観ていて何がどうなっているかわかりません。
ヤング監督は、群衆のふるまいを演出するセンスがないのです。
対するに、ルイス・ギルバートは、「大人数が戦う場面」の交通整理が上手です。それが『二度死ぬ』や『私が愛したスパイ』のクライマックスシーンの高揚を担保しています。この点は、007シリーズの制作の流れにかなりの影響があったと思うのですが、これについていかにお考えでしょうか?
もう一点。ティモシ―・ダルトンは、リアルにボンドを演じた故、かえってボンドが敵を殺すとき、「いちいちこんな風にキレてどうする」と思わせます(笑) この「ダルトンのリアリズム路線がボンド映画にはそぐわなかった」件について、ご意見をお聞かせ願えれば幸いです。
ありがとうございます。先生から、このようなお言葉を頂き、光栄であるとともに恐縮しております。
削除群衆の撮り方についてはごもっともで、ヤングの他の代表作、「暗くなるまで待って」や「夜の訪問者」は、タイマン勝負の緊張感が見事な作品だと思います。対するギルバートは従軍ドキュメンタリー・カメラマン出身で、軍隊という群衆を撮ることから始めています。そのためキャリアの初期は、戦争映画を多く撮っています。
両者の特徴の違いとしては、ギルバートはアクションを撮るのが好きで、ヤングはアクションに至るまでの緊張感を撮ることに長けていたと思います。共同プロデューサーのサルツマンはギルバートの演出を嫌い、「女王陛下の007」を製作します。一方、共同プロデューサーのブロッコリは、ギルバートの演出が好きでした。ですからサルツマンがイオンプロを去ると、すぐにギルバートを招聘して「私を愛したスパイ」を製作したのだと思います。
私はヤングとギルバートの演出の差は、観客ウケという点でギルバートに軍配が上がり、エンタメ路線に本格的に舵を切った原因だったとおもいます。それに合わせて、原作志向のハリー・サルツマンと、娯楽大作志向のアルバート・ブロッコリという全く趣味の異なる共同プロデューサーの主導権争いと、最終的にブロッコリが勝ったことが作品に影響していると考えています。
2つ目のご質問ですが、ティモシー・ダルトンは、暑苦しいですね(笑) ダルトンのリアリズムは、タイミングが最高に悪かったと思います。「リビング・デイライツ」が公開された87年は、ポップミュージックを全編に流し、プロモーションビデオのような映像を主体にしたMTV映画全盛期です。明るくてノリの良さが求められた中で、ダルトンの映画は重すぎたと思います。
冷戦が終結した時期に、よりによってスパイものをハード路線で映画化するというのも、なんともタイミング的にまずかったと思います。なにからなにまで、暑苦しいダルトンを迎えるには条件が悪かったように思います(汗)